本郷氷川神社境内の西、駐車場之入口の脇に、整然と並べて安置されています。元々この地域には幾つかの供養塔があり、その幾つかが集められて供養されていましたが、大戦の戦災により、何れも破損甚だしく、1体を新しく建てて一括供養しました。完全なものは1体のみで、六臂の青面金剛で、最も新しく、昭和45年1月21日に再建立され、安置されています。他では、江戸時代のものと思われる1体は、半ば砕かれ、台座にある三猿のみは認められますが、他のことはさっぱり不明です。またもうひとつの1体は、3分の2ほど破損しているため、詳細はまったく不明です。



庚申塔 3体
2010年6月1日真言宗東寺派百観音明治寺
2010年6月1日
「百観音」とは、どういった観音様を指すのでしょうか。「百観音明治寺」のHPを閲覧すると以下のように記してあります。
『「百観音」とは、近畿一円に広がる西国(さいごく)三十三観音と、関東地方の坂東(ばんどう)三十三観音、それに秩父の周辺に広がる秩父三十四観音の札所 (ふだしょ)を総称したものです。』とあります。
「百観音明治寺」の庭園には、その百ヶ寺にお祀りしてあるそれぞれの観音様方、例えば聖観音 (しょうかんのん)や千手観音 (せんじゅかんのん)、十一面観音 (じゅういちめんかんのん)等々のお姿をいただいて石に刻んだものがあります。
これを「写し霊場(れいじょう)」といいます。現在、「百観音明治寺」の庭園には、番外の観音様も増えて、現在のところ百八十体以上になっていますが、いずれにせよ、ここに居並ぶ観音様をー通り拝んでいると、百観音札所のすべてをお参りするに等しいご利益(りやく)を授かることになります。あるいはこのすべての観音様と、縁結びができると言うこともできるでしょう。

大変残念なことに、写真にあるよう「百観音明治寺」の境内図が、長年の風雨のせいで、ほとんど読み取れません。よって、観音様方の御名前がわかりづらいです。
■「百観音明治寺」では、写真撮影に関して以下の理由で禁止となっていますので、参拝に行かれる方は、ご注意ください。
『当山では、原則として仏像の写真撮影をご遠慮いただいております。これは、写真を撮るということも仏様のお姿を写す「写仏」でございますので、相応の作法や礼儀、心構えを持っていただきたいと考えるためです。』
弥生時代後期復元住居
2010年6月1日

時代を遡ること今から約2千年前、大陸から稲作が伝わると、狩猟採集を中心とした縄文時代が終わり、稲作中心の弥生時代が始まります。そして、現在、平和の森公園がある辺りには、東京都内最大の弥生時代の大集落(農業共同体)であったことが、中野刑務所跡の遺跡発掘調査によって明らかになりました。このあたりの集落には約300軒の竪穴住居や高床式倉庫、首長の墓があったことがわかり、その中の民家1棟が、記念としてここに弥生時代後期復元住居として、復元されています。 この住居ですが、触ってみたらコンクリート製でした。中は、鍵がかかっているために、入れません。

玉井稲荷大明神
2010年6月1日百観音明治寺の入り口の右手にあるのが「玉井稲荷大明神」です。小さくても、立派な、稲荷神をご祭神とする神社です。百観音明治寺の創設者・草野栄照尼が出身地である埼玉県玉井村の稲荷大明神を大正期に勤請したものです。子供の守護神だそうです。


桃園緑道の”お伽話通り”
2010年6月1日桃園緑道の中央2丁目付近は、”おとぎ話通り”となっているのはご存知でしょうか。注意して足元の歩道を見ると、一定の間隔でタイルに絵が描かれています。お子さんと散歩するときに「お伽話」を読み聞かせてあげたら、喜んでもらえると思いますよ。


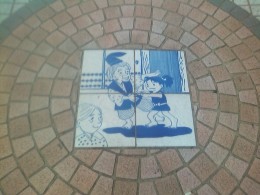






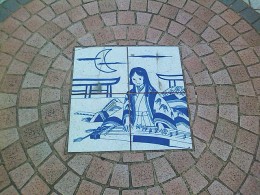
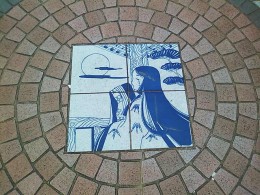
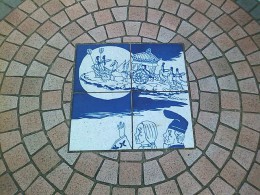
周辺の駐車場
下記駐車場はakippa(あきっぱ!)で予約ができます。
●カーサフォレストーネ東中野駐車場【土日祝のみ】
●柏木ハイツ駐車場
●北新宿4丁目駐車場
●カーザペスカ駐車場
●中野区中央4丁目自宅駐車場
●サンシャインハイツ駐車場
●中野1丁目駐車場【木曜以外】
●コーポクローバー高円寺駐車場
●高円寺南5丁目9akippa駐車場
周辺のスポット
●「神田川」歌碑
●第六天神社
●宝仙寺三重塔跡
●塔山庚申塔(石棒様)
●白玉稲荷大明神
●鎮国山高歩院
●布袋尊石像
●中野・豊川稲荷大明神
●北野神社
●一本槍稲荷神社
●真言宗豊山派善成寺(中野不動)
真言宗豊山派 東光寺
2010年5月31日沿革:当寺は昭和20年5月の戦災によって、本尊薬師如来・脇侍・過去帳および数領の法衣以外の一切を焼失、現在の構築・什物類はすべて戦後の成立である。
寺の生い立ちは江戸時代初期の頃(開山第一世法印秀範和尚は明暦2年12月入滅)。檀徒墓地には、慶安・寛文・貞享・元祿等の立年をもつ墓石が現存、墓地中央部に元祿三年刻銘の施主14人による弥勒半跏像が「為出離三界往生極楽」建立されており、農民の菩提所としての開基が推察される。
その後、五世法印宥真和尚を法流初祖として新義真言宗となり(?)その三世(七世)法印満盛和尚の代には、明和年間に七間半五間半の本堂および庫裡・台所を次ぎ次ぎに構築し寺院としての規模と機能を新たなものとしている。以後九世までの活動ははっきりしない。
明治中期、十世権中僧都宥浄和尚は入山して後地域との連帯・教化につとめ、十一世大僧正浄賢和尚・十二世現住職は檀徒と共にその努力を継ぐ。昭和9年落慶をみた新本堂は不幸にして鳥有に化したものの、戦後の精神界の動揺を憂えて境内の一部に「ひかり幼稚園」を設立し、以後本堂・客殿・庫裡・講堂と順次構築を拡げている。
※中野のお寺 ふれあい広場HPより抜粋




山門をくぐってすぐ左手に池があります。小さな池ですが、鯉が泳いでいます。池の畔には、小さなお堂があり、龍神が祀られています。手水舎の横には合掌した仏様が。
左手には、稲荷神社があり、神仏習合の影響が、この東光寺にも残っています。
山門の手前には、階段状の広い墓所があります。


浄土真宗本願寺派 浄円寺
2010年5月31日

西武新宿線都立家政駅南口を出て、交番の脇の道を西武線の線路沿いに歩くと、入り口が見えてきます。
門柱の案内が無いと、普通の民家のようです。西武線の線路沿いですので、引っ切り無しに西武電車が通過してゆきます。
親鸞聖人は、「やかましい!」と怒らないのかな・・・・。
八幡神社(大和町)
2010年5月31日杉並区の高円寺駅から早稲田通りを横切り、大和町の住宅街の中にある八幡様です。八幡神(はちまんしん・やわたのかみ)は、日本独自に信仰されている、弓矢神(ゆみやかみ)・武神(ぶしん)です。八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)とも呼ばれています。
八幡神を祀る神社は、全国に約2万社ともいわれ、稲荷神社に次いでその数は全国第2位です。
★八幡神社の総本社は、大分県宇佐市にある「宇佐神宮」です。

この大和町の八幡神社は、上沼袋村枝村大場村の鎮守様です。御祭神は、誉田別命(ほんだわけのみこと)です。鳥居が2柱、狛犬が3対あります。1058年に創建され、今年で952年になります。


八幡神社に向かって左手に稲荷神社があります。
鳥居には、稲荷神社としか記されていませんが、参拝の際に中をよく見ると(写真は見づらいですが)「むすび稲荷」とあります。



厄除不動堂と育英地蔵堂
2010年5月31日 


大和町の八幡神社の横には、厄除不動堂と育英地蔵堂の2つがあり、それぞれ、地域の人々に愛されています。2つの御堂にそれぞれ鎮座している不動明王とお地蔵様は、人々の健康と長寿を願い、子供が健やかに育つように願い、今日も優しく見守ってくれています。育英地蔵と書きますが読み方は、「こそだてじぞう」です。
真言宗豊山派 光徳院
2010年5月28日沿革:
当院は開山当時は半蔵門にあったが、江戸城構築に際し寛永年間、牛込市ヶ谷田町に転じ、さらに同所柳町に移り、明治43年、第27世・隆芳和尚の時この地に移る。
寺宝の千手観世音は木像で高さ3尺3寸。子育観音と号し、第60代醍醐天皇の御代、延喜元年、右大臣・菅原道真公が筑紫へ左遷のみぎり自ら刻みて供養礼拝した。
その後、久しく筑紫の千手坊にあったが、寛永13年、越前宰相・忠昌侯に男子出生し、ト者をして相せしむところ千手観世音の化体なりと言った。この男子、仙菊丸と言い長じて松平中務大輔昌勝となる。
また仙菊丸の母公も夢に観世音が築紫の千手坊にあるを見る。この時、家臣を築紫につかわせ越前福井の城中へ迎え、仙菊丸の守護本尊として身体安全息災延命を祈った。
その後、縁あって中野宝仙寺の14世秀雄法印にあづける。秀雄法印は中野宝仙寺より、光徳院に転住となり、尊像を守護して一宇を建立し安置した。この時より諸人の参拝を許すようになった。
※中野のお寺 ふれあい広場HPより抜粋


山門をくぐると、すぐ右手にお地蔵様が鎮座しています。


本堂の手前右には、「観音堂」が、左手には何と「五重塔」が建っています。この五重塔は、木像瓦葺きで造られ、仏塔愛好家が全国から参拝に見えるほどです。


観音堂と五重塔を左右に、本堂があり、プチ京都の雰囲気です。
